不思議日本仏教謎解講座
2018-10-8 来源:本站原创 浏览次数:次このごろわたしは、よく韓国の寺めぐりに行きます。日本に仏教を伝えたのは朝鮮半島からやってきた人々ですから、両国の寺や仏教のあり方はよく似ているはずです。しかし、実際に行ってみると、まったく違う面もたくさんあります。見た目の違いも数々ありますが、もっとも大きな違いは、韓国のお坊さんは妻帯をしないということです。
日本のお坊さんは、妻帯もし、肉も食べて、比較的一般人に近い生活をしている人が多いようですが、仏教の基本に立ち返れば、出家して僧となった人は、仏教の戒律に従って妻帯も肉食もしないはず。つまり日本の僧侶のあり方は、他の国から見れば、かなり特異なものです。
日本の多くの寺では、住職は世襲です。しかし、僧侶が妻帯をしない国では、当然ながら子供もいないので、世襲はあり得ません。僧侶は自分の意思で普通の生活を捨て、僧侶になることを選ぶのです。
檀家制度も日本独特のものである
韓国では、昔ながらのお参りを目的に寺に行く人が多く、日本では、法事や墓参り、もしくは、観光のために寺に行く人が多い(韓国 海印寺にて撮影)檀家制度とは、ある家族が先祖代々ひとつの寺に属し、葬儀や法事などの一切をその寺に任せることです。
韓国の僧侶は妻帯をしないため、世襲ではなく、自発的に修行して僧侶になる
これは江戸時代初期に幕府や諸大名たちによって制定された制度です。それ以前にも、貴族や有力な武家などが氏寺を作ることはよくありましたが、庶民が檀家となって寺に属することが一般的になったのは、17世紀の中ごろからです。
なぜこの制度が生まれたか。それは、隠れキリシタンを撲滅するためです。住民は寺に所属し、生き死にに関するすべてを寺に任せ、おりあるごとに寄進をします。その引き換えに、寺は、その人物が檀家であり、隠れキリシタンでないことを証明します。それほどに、幕府はキリスト教が広まることを恐れていたのです。
韓国では、昔ながらのお参りを目的に寺に行く人が多く、日本では、法事や墓参り、もしくは、観光のために寺に行く人が多い(韓国 海印寺にて撮影)
寺は法事や葬式だけでなく、檀家の人々の戸籍を預かり、結婚や転居の手続きもしました。要するに、江戸時代以降の日本の寺は多くが役所のようなもので、その風習の一部である葬式や法事が今でも続いているため、日本の仏教は、時に「葬式仏教」と揶揄されるようにもなったのです。
(この文章がいいと思うなら、友達に分かち合ってください。)
开眼看七洲
志在游与学
▼
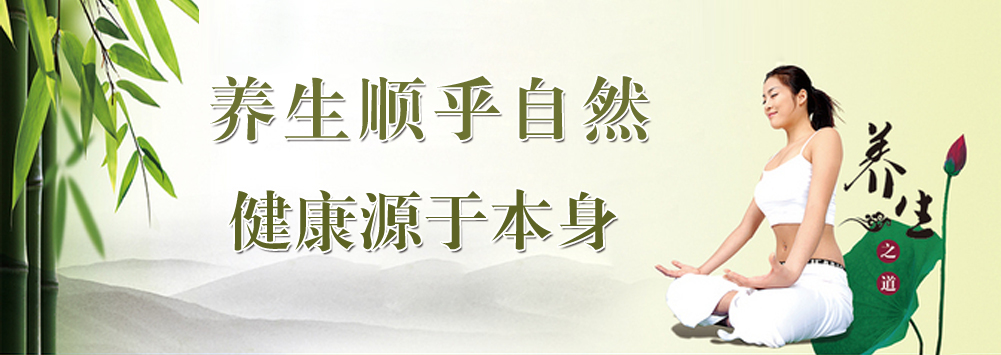
 健康热线:
健康热线: